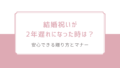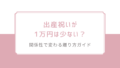結婚祝いに現金とプレゼント、どちらを贈るかで迷う方は多いです。友人に現金を贈る際のマナーや、プレゼントのみを贈る場合の選び方、ご祝儀とは別にプレゼントを用意する際の金額の目安といった判断ポイントは複数あります。
さらに、お金にお菓子を添える贈り方や現金の手渡し方法、現金が失礼に当たるケース、両方を贈るときの送り方や相場、3000円の結婚祝いが失礼にあたるのかなど具体的な金額感も気になるところでしょう。
この記事では、相手との関係性や状況に合わせて現金・プレゼント・両方のいずれを選ぶべきかを、分かりやすく丁寧に解説します。
- 結婚祝いで現金とプレゼントのどっちを選ぶべきかの判断基準
- 関係性別に適した金額と贈り方のポイント
- 現金やプレゼントを渡す際のマナーや注意点
- 現金とプレゼントを組み合わせるときの実践的な方法
結婚祝いは現金かプレゼントどっちが正解?迷ったときの考え方
- 結婚祝いに現金を友人へ贈る場合のマナー
- 結婚祝いでプレゼントのみを渡すのはあり?
- ご祝儀とは別にプレゼントを贈る時の金額の目安
- 結婚祝いでお金とお菓子を組み合わせる贈り方
- 現金を手渡しする時のタイミングと注意点
- 結婚祝いで現金が失礼にならない渡し方
結婚祝いに現金を友人へ贈る場合のマナー

友人への結婚祝いとして現金を贈る際は、金額の妥当性や渡し方のマナーに細心の注意を払うことが大切です。一般的な相場は3万円前後とされていますが、これは多くの冠婚葬祭マナー書や結婚情報誌でも共通して示されている基準です。特に親しい友人や学生時代からの付き合いが長い相手には、5万円程度を包むケースも珍しくありません。ただし、奇数は「割れない=縁が切れない」とされるため、2万円や4万円などの偶数は避けるのが通例です。
のし袋は「寿」または「御結婚御祝」と書かれた結び切りかあわじ結びのものを選びましょう。中袋には金額と氏名を明記し、筆ペンや毛筆で丁寧に記入します。新札を用意するのは、「新しい門出を祝う」意味が込められているためです。銀行や郵便局で両替する際には、事前に新札を確保しておくと安心です。
披露宴に出席する場合は、受付でのし袋を差し出すのが一般的で、出席しない場合には直接訪問して渡す、または現金書留を利用する方法が適しています。現金書留封筒を使用する際は、のし袋ごと入れ、折れや汚れがないように注意します。
また、地域や家族間の慣習によって金額の感覚が異なる場合もあるため、事前に身近な人へ確認しておくのも良いでしょう。なお、結婚関連の支出に関する統計は、総務省統計局の「家計調査」にも掲載されており、一般的な祝い金の水準を知る参考になります(出典:総務省統計局『家計調査』)。
結婚祝いでプレゼントのみを渡すのはあり?
結婚式に招待されていない場合や、ご祝儀を渡す機会がないときは、「プレゼントのみ」を贈るのも自然で一般的な方法です。この場合の相場は5000円〜1万円が目安とされ、関係性や年齢層によっても変動します。友人・同僚へのプレゼントなら5000円前後、親しい友人や親族には1万円前後の品が妥当です。
プレゼント選びでは「実用性」と「新婚生活のサポート」を意識すると喜ばれやすくなります。たとえば、ペア食器、名入れのワイングラス、人気の家電ブランドのコーヒーメーカーなどが定番です。特に、新生活を始めたばかりのカップルには、日常的に使えるアイテムが高く評価されます。最近では、ギフトカードや電子カタログギフトも人気を集めています。これにより、相手が自由に欲しいものを選べる利点があります。
ただし、高価すぎる贈り物はかえって相手に気を遣わせることがあります。一般的に、相場を大きく超える品物(2万円以上)は避けた方が無難です。複数人でプレゼントを共同購入する場合は、贈り主全員の名前をカードに記載し、贈り主と受け取り側双方にとって気持ちよくやり取りできる形に整えるのが理想です。
また、贈る時期にも配慮が必要です。結婚式の招待を受けていない場合は、結婚式が終わって1カ月以内、もしくは結婚報告を受けてから1カ月以内に渡すと良いでしょう。タイミングを逃すと「今さら感」が出てしまうため、節度を持った時期に贈るのがマナーです。
ご祝儀とは別にプレゼントを贈る時の金額の目安

ご祝儀とは別にプレゼントを贈る場合は、「ご祝儀+プレゼント」の総額が適切なバランスになるよう調整するのが基本です。ご祝儀を3万円包むなら、プレゼントは5000円〜1万円程度が一般的な目安です。これは、多くのマナーサイトや冠婚葬祭ガイドでも共通して推奨されている水準です。
たとえば、友人や同僚の場合は5,000円前後の実用品、親友や兄弟姉妹には1万円前後の特別感のあるギフトを選ぶのが良いでしょう。親族間では、家電や家具など、やや高額でも実用的なものが選ばれる傾向にあります。逆に、会社関係者やビジネス上のつながりがある相手には、あまり個人的すぎる品物よりも、消耗品や上品な贈答品(高級菓子や紅茶セットなど)が好まれます。
また、「ご祝儀を現金で包む+プレゼントを添える」という形式は、相手への敬意と感謝をダブルで表現できるメリットがあります。ただし、トータルの金額が高くなりすぎると、相手に心理的な負担を与えてしまう可能性があります。相手との関係性・年齢差・職場での立場などを考慮し、「気持ちが伝わる範囲」に留めることが重要です。
なお、郵送でプレゼントを贈る場合には、壊れやすい品を避け、熨斗紙やメッセージカードを添えると丁寧な印象になります。特にのしの表書きは「御結婚御祝」とし、氏名を楷書体で記入するのが正式です。マナーを守ることで、形式だけでなく、贈る側の誠意や信頼性も伝わります。
結婚祝いでお金とお菓子を組み合わせる贈り方
結婚祝いでは、現金にお菓子を添えるスタイルが上品で心のこもった贈り方として好まれています。現金だけでは形式的な印象を与えることもありますが、お菓子を加えることで「幸せを分かち合う」という象徴的な意味が加わり、より温かみのある贈り物になります。特に日本では、お菓子に「喜びを共有する」「甘い生活を願う」といった縁起の良い意味が込められています。
選ぶお菓子は、日持ちのする焼き菓子や高級感のある和菓子が最適です。たとえば、フィナンシェやマドレーヌなどの個包装された洋菓子は清潔感があり、配りやすい点も評価されています。和菓子なら、紅白饅頭や最中、上品な羊羹の詰め合わせが定番です。特に、紅白や金銀を基調とした包装は祝いの席にふさわしく、結婚祝いとして見た目にも華やかです。
お菓子を選ぶ際には、相手の家族構成や嗜好を考慮することも大切です。たとえば、甘いものが苦手な相手には、ナッツやおかき、紅茶などを添えるのも良い方法です。また、賞味期限が短い生菓子や冷蔵品は避け、常温保存が可能な商品を選ぶことで、贈られた側の負担を軽減できます。
職場など複数人で結婚祝いを渡す場合、お金とお菓子をセットにすることで、形式的になりすぎず柔らかい印象を与えます。見た目も華やかで、チーム全体の気持ちを表しやすい点も魅力です。贈り方としては、のし袋とお菓子の箱をまとめてラッピングするか、現金を封筒に入れてお菓子に添える形が一般的です。お菓子の外箱にメッセージカードを添えると、より丁寧な印象になります。
このように、お菓子を添えることで形式と心遣いの両方を表現できるため、現金のみの贈り物よりも印象が柔らかくなります。結婚という人生の節目にふさわしい贈り方の一つと言えるでしょう。
現金を手渡しする時のタイミングと注意点

現金を手渡しする場合、最も重視されるのは「渡すタイミング」と「渡し方の丁寧さ」です。まず、結婚式に出席する場合は、受付で渡すのが一般的なタイミングです。その際は、のし袋の表書き(「寿」または「御結婚御祝」)と氏名の記載を事前に確認し、中袋に金額を明記しておきましょう。封筒内の現金は必ず新札を使用し、向きを揃えることで誠意を示せます。
直接手渡しする場合は、相手が忙しくないタイミングを選ぶことが大切です。結婚式の前日や当日の受付以外では、挙式の1〜2週間前に訪問して渡すのが一般的です。その際には、封筒の向きを相手側に向け、両手で丁寧に差し出します。手渡しする際の言葉も重要で、「ご結婚おめでとうございます。お幸せをお祈りしています。」など、祝福の言葉を添えると良い印象を与えます。
一方、直接会う機会がない場合や遠方に住んでいる場合は、現金書留を利用するのが安全で確実な方法です。現金書留用封筒は郵便局で購入でき、金額に応じて補償が付くため安心です。封筒の中には、のし袋ごと入れ、折れや汚れがつかないように保護しましょう。メッセージカードを同封することで、形式だけでなく気持ちも伝わりやすくなります。
また、汚れた封筒や折れたお札は縁起が悪いとされるため避けましょう。細かい気配りが、相手に対する真摯な姿勢を示します。なお、現金書留の扱いや郵便の安全性に関する情報は、日本郵便の公式サイトにて確認できます(出典:日本郵便『書留』)。
結婚祝いで現金が失礼にならない渡し方
結婚祝いとして現金を贈ることは非常に一般的であり、決して失礼ではありません。しかし、相手との関係性や立場によっては、渡し方を誤ると事務的・無機質な印象を与えてしまうことがあります。そのため、「どのように渡すか」という配慮が何より重要です。
たとえば、上司や目上の方に現金を渡す場合には金額の設定に注意が必要です。高額な現金は、「目下の人に施しを与える」という意味を持ち、失礼に当たる場合があります。迷った場合は、現金ではなくプレゼントを選ぶのが無難です。
また、現金を渡す際はのし袋の種類にも注意が必要です。結婚祝いの場合は「寿」と書かれた紅白結び切りののしを使用します。これは「一度きりのお祝い」を意味しており、再び結び直さないという結婚にふさわしい形です。水引が蝶結びのものは、出産祝いや入学祝いなどの「何度あっても良い祝い事」に使われるため、用途を誤らないようにしましょう。
さらに、渡すタイミングや場所も印象を左右します。披露宴当日の受付での受け渡しが最も一般的ですが、出席しない場合は結婚報告を受けた時点で早めに渡すのがマナーです。遅すぎると「お祝いを忘れていた」と受け取られる可能性があるため注意しましょう。
このように、現金を贈ること自体は決して失礼ではなく、むしろ日本では最も実用的で誠実な祝い方とされています。大切なのは、金額や渡し方のマナー、そして相手への思いやりを形にする工夫です。気持ちをきちんと表現することで、現金というシンプルな贈り物でも温かさが十分に伝わります。
結婚祝いは現金かプレゼントのどっちを選ぶ?関係別の判断基準
- 結婚祝いで現金とプレゼントを両方を贈るケース
- 現金とプレゼントの両方を贈る時の送り方マナー
- 3000円の結婚祝いが失礼にあたる場合とは
- 結婚祝いの相場を関係性別に解説
- 結婚祝いで現金とプレゼントの両方を贈る際の注意点
結婚祝いで現金とプレゼントを両方を贈るケース

結婚祝いとして現金とプレゼントを両方贈るのは、特に親しい友人、兄弟姉妹、あるいは長年の付き合いがある同僚など「特別な関係性」を持つ相手に最も適した方法です。ご祝儀という形で金銭的なお祝いを伝えつつ、プレゼントで個人的な気持ちを添えることで、形式と心の両面をバランス良く表現できます。
この組み合わせは、単に「金額を増やす」という意味ではなく、「相手の新しい生活を応援したい」という思いを形にする手段です。たとえば、ご祝儀を3万円包み、そこに1万円程度のプレゼント(家電や食器、インテリア雑貨など)を添えるケースが一般的です。特に、新居への引っ越しや新生活のスタートを支援する実用品は喜ばれやすい傾向にあります。
ただし、全体の金額が高くなりすぎると、相手に心理的な負担を与える場合があります。一般的には、ご祝儀+プレゼントの合計が5万円以内に収まるように調整するのが無難です。特に親族間では「ご祝儀5万円+プレゼント1万円程度」まで許容されることもありますが、友人関係や同僚関係では3万円前後を目安にしましょう。
また、両方を贈る場合には、「式に参加するか」「事前に渡すか」など、渡すタイミングによって内容を調整することも大切です。式に出席するならご祝儀をメインに、式に呼ばれていない場合はプレゼントを中心に据えた方が自然です。相手の状況に合わせて形式を柔軟に変えることが、マナーある贈り方といえます。
現金とプレゼントの両方を贈る時の送り方マナー
現金とプレゼントを同時に贈る際には、それぞれの「贈り方の形式」を正しく守ることが大切です。まず、ご祝儀は必ず紅白結び切りののし袋を使用し、表書きには「寿」または「御結婚御祝」と記載します。現金は新札を準備し、中袋には金額と氏名を丁寧に書きます。
プレゼントの包装も見落とせないポイントです。祝い事にふさわしい白や金、ピンクなどの柔らかい色合いの包装紙を選び、リボンは紅白または金銀の組み合わせが無難です。結婚祝いにふさわしくない色(黒・青・灰色など)は避けましょう。プレゼントにはのしを付ける場合と付けない場合がありますが、フォーマルな相手や職場関係ではのしを添え、「御結婚御祝」と記載するのが望ましいです。
手渡しの際は、「お祝いの気持ちを込めて、ささやかな品を添えました」とひとこと添えることで、贈り物に込めた心が自然に伝わります。ご祝儀を渡すときには先にのし袋を差し出し、その後にプレゼントを渡すのが正しい順序です。
郵送で贈る場合には、現金とプレゼントを一緒に送るのは避け、現金書留で現金のみを送り、プレゼントは別便で発送するのがマナーです。現金書留の封筒内には、メッセージカードを添えると丁寧な印象になります。現金書留の制度や補償内容の詳細は、日本郵便の公式サイトで確認できます(出典:日本郵便『書留』)。
このように、現金とプレゼントを分けて丁寧に扱うことが、形式と安全性の両面で最も望ましい方法です。
3000円の結婚祝いが失礼にあたる場合とは
「3000円の結婚祝い」は、状況次第で適切にも失礼にもなり得ます。金額だけを見ると少額に感じますが、贈るシーンと相手との関係性によって意味が大きく変わるため、一概に「失礼」とは言えません。
たとえば、披露宴に出席する場合は、料理・引き出物の費用を考慮してご祝儀の相場は友人で3万円、同僚で2〜3万円が一般的です。そのため、3000円では費用の一部にも満たず、「形式を欠いた」と捉えられる可能性が高くなります。このような正式な式典や披露宴では、3000円の金額設定は避けるのが無難です。
一方で、披露宴に招かれていない場合や、カジュアルなお祝いとして気持ちを伝える場合には、3000円でも十分に適切です。たとえば、同僚や後輩が結婚する際に、ランチ会や職場でのお祝いとしてお菓子やギフトカードを添えるケースでは、3000円程度が程よいバランスです。贈り物にメッセージカードを添えると、金額以上に温かみのある印象を与えることができます。
また、地域や年齢層によっても「お祝い金の感覚」は異なります。特に20代の若手社会人の場合、3000円〜5000円程度のプレゼント付きギフトが相場となることもあります。重要なのは、金額の多寡ではなく「場に合った心遣い」が感じられるかどうかです。
このように、3000円の結婚祝いは「正式な式典」では不適切ですが、「軽いお祝い」や「職場の気持ちを伝える場」ではむしろ自然な選択です。金額の印象にとらわれすぎず、相手との関係や贈る場の雰囲気を考慮して選ぶことが、マナーの本質といえるでしょう。
結婚祝いの相場を関係性別に解説

結婚祝いの金額は、「どのような関係の相手に贈るか」によって大きく変わります。形式上のマナーだけでなく、地域の慣習や年齢層、経済的な立場も考慮する必要があります。以下は全国的に見て一般的とされる目安です。
| 関係性 | 相場金額 |
|---|---|
| 友人・同僚 | 2〜3万円 |
| 兄弟姉妹 | 3〜5万円 |
| 親族(いとこ・甥姪など) | 5〜10万円 |
| 上司・目上の人 | 1〜3万円 |
| 知人・ご近所・取引先など | 5000円〜1万円 |
この表はあくまで「平均的な全国相場」であり、実際の金額は地域差や慣習によって異なります。たとえば、関西圏ではご祝儀がやや少なめ、関東圏では多めに包む傾向があります。また、地域の冠婚葬祭文化や年齢層によっても判断基準が変わることがあります。
経済産業省が公表している家計調査データによると、日本国内では冠婚葬祭費としての年間支出が平均で約6万円前後となっており(出典:総務省統計局『家計調査』)、この中でも結婚祝いは大きな割合を占める支出項目です。この統計を参考に、自身の経済状況とのバランスを考えながら金額を設定すると良いでしょう。
特に注意したいのは「グループで贈る場合」です。友人同士や同僚数人でまとめて贈る際は、全体で2〜3万円程度になるように調整し、ひとりあたりの負担が軽くなるようにするのがスマートです。金額を合わせる際は、代表者が集金し、のし袋には全員の名前を記載するか、「〇〇一同」とまとめて表記します。
このように、結婚祝いの相場は単なる金額の問題ではなく、「相手への敬意」と「社会的な礼儀」を示す行為でもあります。地域の慣習や職場の雰囲気を確認しつつ、心を込めて準備することが大切です。
結婚祝いで現金とプレゼントの両方を贈る際の注意点
現金とプレゼントを併せて贈る場合は、「金額のバランス」と「渡すタイミング」の2点を特に意識する必要があります。両方を贈ることは非常に丁寧な印象を与えますが、贈り方を誤ると相手に気を遣わせてしまうこともあります。
まず、トータルの金額設定ですが、ご祝儀+プレゼントの合計が5万円以内に収まるのが一般的です。たとえば、ご祝儀3万円に加えて1万円程度のプレゼント(食器セットや調理家電、ペアグラスなど)を添えると、華やかさを保ちながらも負担のない範囲になります。
また、贈るタイミングも非常に重要です。式当日に現金をご祝儀として渡し、プレゼントは事前(1週間〜10日前)に贈るのが最も理想的なマナーです。式の直前や直後に重なると、相手が荷物の管理やお礼対応に追われるため、かえって負担になってしまうことがあります。もし式に招待されていない場合は、入籍報告を受けたタイミングや新居が整った頃にプレゼントを郵送するのがスマートです。
さらに、プレゼントを選ぶ際には「重複防止」も大切なポイントです。最近では、カップルが希望のギフトを事前に登録できる「ギフトレジストリ」サービス(例:Amazon Wedding Registryなど)を利用するケースも増えています。これらを確認できる場合は、相手の希望に沿った贈り物を選ぶのが確実です。
もしリクエストを直接聞けない場合でも、同じ職場や共通の友人などを通じて、他の人が何を贈る予定かを確認しておくと安心です。特に家電やブランドアイテムは重複しやすいため注意が必要です。
最後に、現金とプレゼントを別々に贈る場合は、それぞれにお祝いのメッセージを添えることが印象を良くします。たとえば、プレゼントには「末永く幸せな家庭を築かれますように」といったメッセージカードを添えると、形式的にならず、温かみが伝わります。
このように、現金とプレゼントを組み合わせる際には、金額のバランス・タイミング・心配りの3点を意識することで、相手に負担を与えず、喜ばれるお祝いを実現できます。
↓相手の欲しいものがわからない場合は、体験を贈るという方法もあります。新婚の相手にとって思い出作りができる贈り物は喜んでもらえる可能性が高いです。
まとめ:結婚祝いは現金とプレゼントのどっちを選ぶべきか
- 結婚祝いは関係性や状況によって最適な形が変わる
- 友人には現金でもプレゼントでも喜ばれることが多い
- ご祝儀とは別にプレゼントを贈る際は金額のバランスが大切
- 現金のみの場合は新札とマナーを守ることが信頼につながる
- お金とお菓子の組み合わせは温かみのある贈り物の方法
- 現金を手渡しする際は封筒や渡し方の所作に注意が必要
- 現金とプレゼントを両方贈る場合はトータル金額に注意する
- プレゼントは実用性や新婚生活に役立つ品が好まれる
- 3000円の贈り物は関係性に応じて判断する
- 結婚祝いの相場は関係性と地域で異なる
- 郵送時は現金書留とプレゼントを別々に送る
- 金額よりも気持ちとマナーを重視することが大切
- 迷ったら現金と小さなプレゼントの組み合わせが無難
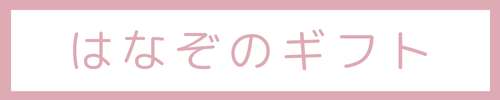
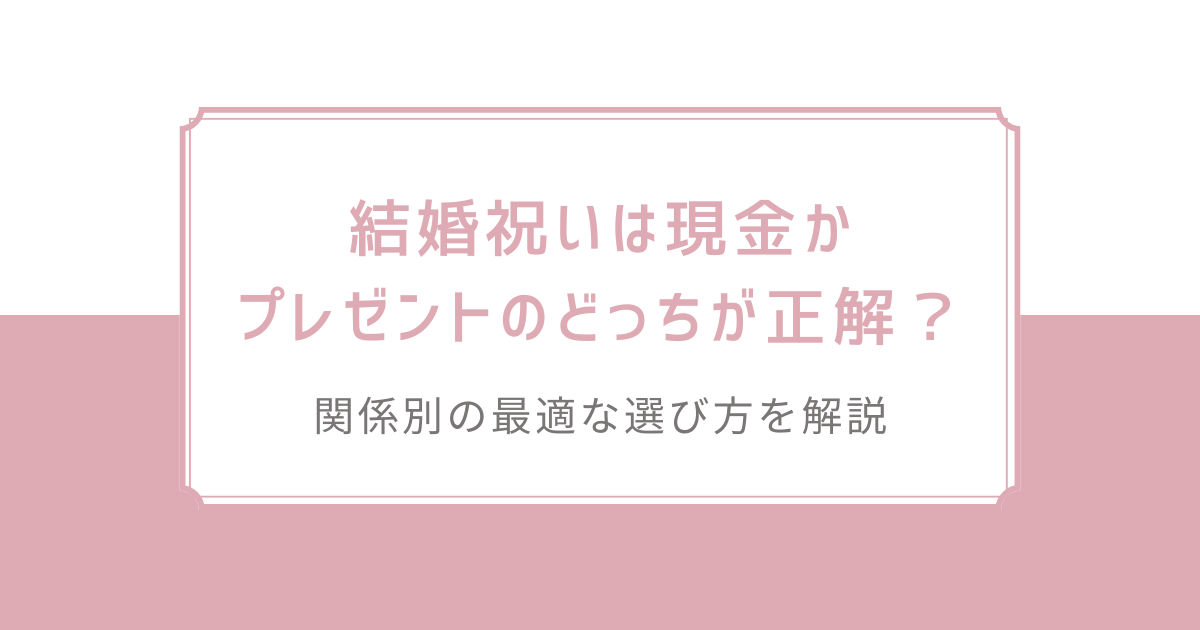
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3c6d940c.d2125612.3c6d940d.0b8fd9bf/?me_id=1215297&item_id=10013190&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbellevie-harima%2Fcabinet%2F1201%2Fgift%2Fcatalog5800_bs.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)