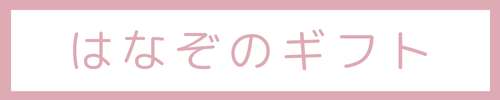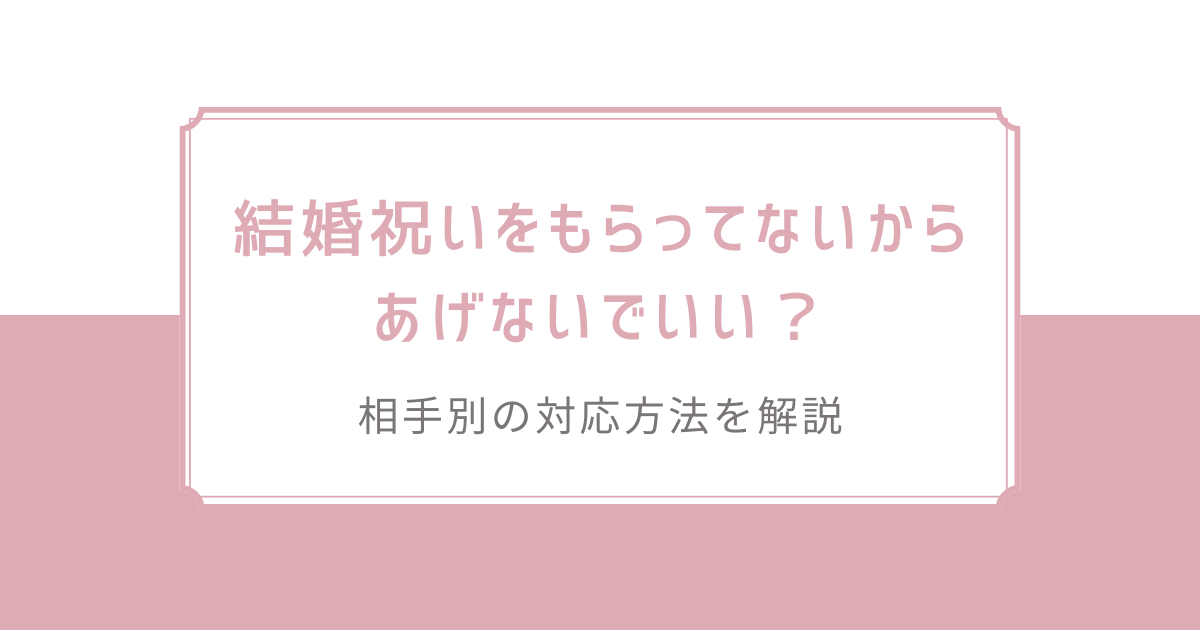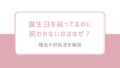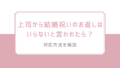結婚祝いをもらっていない相手に対して、自分もお祝いをあげるべきか迷うことはありませんか。兄弟や親戚、友人など、関係性によって対応が異なるため、どうすればよいか悩む人は多いです。
特に、結婚式をしないとお祝いをもらえないのか、結婚式を欠席した相手からご祝儀をもらっていない場合はどうするべきかといった疑問を持つ人もいるでしょう。また、結婚祝いをもらっていない人の結婚式に招待されたときや、お祝いをくれなかった人の結婚式に出席する際の対応に悩むこともあります。
ご祝儀をもらっていないから自分もあげないのは失礼なのか、金額の調整は可能なのか、嬉しかったものとしてどのような結婚祝いがあるのかも気になるところです。
本記事では、結婚祝いをもらっていない場合の対応や考え方について、具体的なケースごとに解説します。
- 結婚祝いをもらっていない場合の対応方法を理解できる
- 兄弟や親戚、友人ごとの考え方の違いを知ることができる
- 結婚祝いを渡すかどうかの判断基準が分かる
- ご祝儀やお祝いの金額の決め方について学べる
結婚祝いをもらってないからあげないのはアリ?
- 兄弟から結婚祝いをもらってない場合の対応
- 親戚からもらってないときの考え方
- 友人がくれない場合の理由と対処法
- お祝いをくれなかった人の結婚式、どうする?
- 相手が結婚式を欠席してご祝儀をもらってない時の対応
兄弟から結婚祝いをもらってない場合の対応
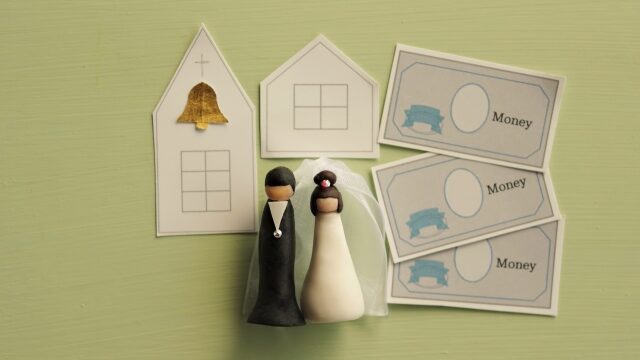
兄弟から結婚祝いをもらえなかった場合、まずは状況を冷静に考えることが大切です。結婚祝いは必ずしも渡すべきものではなく、家庭ごとの価値観や経済的な事情が関係している可能性があります。
一方で、兄弟間でお祝いのやり取りをする習慣があるにもかかわらず、自分のときだけもらえなかった場合は、なぜそうなったのかを確認してみるのもよいでしょう。例えば、兄弟が単純に忘れていたり、「身内だから不要」と考えていたりするケースもあります。
このような場合、まずはさりげなく「お祝いってどうしてる?」と聞いてみるのも一つの方法です。また、自分が今後お祝いを贈るべきか迷う場合は、相手の結婚時の対応を参考にするのもよいでしょう。無理にお祝いを催促するのではなく、お互いにとって違和感のない関係を築くことが大切です。
親戚からもらってないときの考え方
親戚から結婚祝いをもらえなかった場合、まずは相手の立場や家族の方針を考えることが大切です。親戚付き合いは家庭ごとに異なり、親しい関係であればお祝いを贈るのが一般的ですが、そうでない場合は「特に決まりがない」と考えていることもあります。
また、相手が高齢である場合や経済的に厳しい状況にある場合、そもそも結婚祝いを贈る文化がない家系の場合もあります。そのため、「もらえなかった=自分が軽んじられている」と決めつけずに、状況を広い視点で見ることが大切です。
どうしても気になる場合は、両親や他の親戚に「親戚間では結婚祝いを贈る習慣があるのか」を確認してみるのもよいでしょう。また、将来的に自分が親戚へお祝いを贈るべきか迷う場合は、今回の状況を参考にして柔軟に対応するとよいでしょう。
友人がくれない場合の理由と対処法
友人から結婚祝いをもらえなかった場合、その理由はいくつか考えられます。まず、単純に「忘れていた」ケースです。結婚式を挙げた場合は、ご祝儀という形でお祝いを渡すのが一般的ですが、式を挙げなかった場合は「何を贈ればいいかわからなかった」「特に必要ないと思った」と考えている可能性があります。
また、経済的な事情が理由の場合もあります。友人自身が金銭的に余裕がないと、お祝いを贈ることを躊躇することがあります。さらに、友人関係の温度差も関係することがあります。自分は親しいと思っていても、相手にとっては「そこまで深い付き合いではない」と感じている場合、あえてお祝いを渡さない選択をすることもあるでしょう。
対処法としては、まず「お祝いをもらうのが当然」と考えすぎないことが重要です。お祝いはあくまで気持ちであり、強制するものではありません。それでも気になる場合は、今後の関係性を考え、友人の結婚時にどのように対応するかを決めるとよいでしょう。無理にお祝いを贈らなくても、心からの祝福の言葉を伝えるだけでも十分です。
お祝いをくれなかった人の結婚式、どうする?

自分の結婚時にお祝いをくれなかった人から結婚式の招待を受けた場合、どのように対応するか迷うことがあります。まず、結婚祝いは義務ではなく、相手にもさまざまな事情があった可能性があるため、「もらっていないから出席しない」と即決するのは避けたほうがよいでしょう。
出席する場合は、ご祝儀をどうするかを考える必要があります。一般的に、ご祝儀は食事や引き出物の費用を考慮して用意するものですが、「自分のときにはもらっていないのに…」と感じる場合は、金額を調整するのも一つの方法です。
一方で、結婚祝いをもらえなかったことが心に引っかかる場合や、相手との関係が希薄である場合は、無理に出席する必要はありません。「都合がつかない」と丁寧に断るのも、ひとつの選択肢です。大切なのは、自分が納得できる形で対応することです。
相手が結婚式を欠席してご祝儀をもらってない時の対応
結婚式に招待した相手が欠席し、ご祝儀をもらえなかった場合、どのように対応するかは関係性によって異なります。通常、欠席する場合はご祝儀を渡すのがマナーとされていますが、それを強制することはできません。相手が忘れている可能性もあれば、「出席しないのにお金を包むのは負担」と考えている場合もあります。
また、相手が体調不良や仕事の都合など、やむを得ない理由で欠席した場合、お祝いの準備まで手が回らなかった可能性も考えられます。そのため、特に親しい間柄であれば「無理をしないでね」と気遣いの言葉を伝えることが大切です。
もし、今後の関係性を考えた上で相手の結婚式に招待された場合は、「自分のときにはご祝儀をもらっていないから」と意識しすぎず、純粋にお祝いの気持ちで行動することが望ましいでしょう。
結婚祝いをもらってないからあげないのは非常識?
- ご祝儀をもらってないのにあげるべき?
- 結婚式をしないとお祝いはもらえない?
- 結婚祝いが誰からもない場合の対処法
- もらって嬉しかった結婚祝いとは?
- 結婚祝いの金額はどう決める?
ご祝儀をもらってないのにあげるべき?

自分の結婚時にご祝儀をもらわなかった相手に対して、相手の結婚式でご祝儀を渡すべきかどうか迷うことがあります。この場合、まず考えるべきなのは、「ご祝儀はあくまで気持ちである」ということです。
一方で、「もらっていないのに渡すのは不公平では?」と感じることもあるでしょう。その場合は、相手が意図的に渡さなかったのか、それとも単に事情があって渡せなかったのかを考えてみることが大切です。
例えば、親しい友人であれば「過去のことにこだわらずお祝いしたい」と考えて、ご祝儀を包むのも自然です。ただし、そこまで親しくない場合や、過去の対応に納得できない場合は、最低限のマナーを守りつつも、ご祝儀の金額を調整するのも一つの方法です。重要なのは、自分が後悔しない選択をすることです。
結婚式をしないとお祝いはもらえない?
結婚式をしない場合、お祝いをもらえるかどうかは周囲の考え方によります。一般的に、結婚式に出席するとご祝儀を渡すのが慣習ですが、式を挙げない場合は「何をどのタイミングで渡せばいいのか分からない」と考える人も多いです。
また、結婚のお知らせをする範囲によっても変わります。例えば、家族や親しい友人には報告していても、職場関係など広い範囲には知らせていない場合、そもそも周囲が結婚を知る機会がなく、お祝いを渡すタイミングを逃してしまうこともあります。
このような状況を避けるためには、結婚の報告をした際に「結婚式はしませんが、〇月に入籍しました」と伝えることで、相手がお祝いを考えるきっかけになります。ただし、お祝いはあくまで相手の気持ちによるものなので、「式を挙げないからもらえないのは当然」と割り切ることも大切です。
結婚祝いが誰からもない場合の対処法

結婚を迎えたにもかかわらず、誰からも結婚祝いをもらえないと、寂しさや戸惑いを感じることがあります。しかし、必ずしも「祝ってもらえない」というわけではなく、単に報告の仕方や相手の状況によって左右されることが多いです。
まず、結婚の報告が十分に伝わっているか確認しましょう。特に結婚式を行わない場合は、周囲が「いつ、どのようにお祝いすればいいのか分からない」と思っている可能性があります。親しい人に対しては、入籍の報告を改めて伝えることで、お祝いのきっかけを作ることができます。
また、お祝いは「もらうことが当然」ではなく、相手の気持ちに委ねられるものです。状況によっては、経済的な理由や忙しさで準備ができなかった人もいるでしょう。そうした事情を理解し、自分からは気にしすぎないことも大切です。
もし、「祝ってもらえないのが悲しい」と感じるなら、自分から周囲をお祝いする側に回るのも一つの方法です。こちらからお祝いを贈ることで、相手も「次は自分もお祝いしよう」と思うかもしれません。
もらって嬉しかった結婚祝いとは?
結婚祝いとしてもらって嬉しいものは、人それぞれ異なりますが、実用的なアイテムや思い出に残る贈り物は特に喜ばれる傾向があります。
たとえば、新生活に役立つキッチン用品や家電は、多くの人にとって実用的で嬉しいプレゼントです。特に、自分ではなかなか買わないけれどあると便利なアイテム(高品質なフライパンやおしゃれなコーヒーメーカーなど)は、もらうと重宝することが多いです。
一方で、体験型ギフトや旅行券なども人気があります。結婚生活が始まると、日常に追われて二人でゆっくり過ごす時間が減ることもあります。そんなときに「ペアディナー券」や「温泉旅行のギフト券」などがあると、特別な時間を楽しむきっかけになります。
また、手作りのアルバムやメッセージが添えられたプレゼントなど、気持ちが込められた贈り物も感動を呼びます。結婚祝いは物だけでなく「お祝いしてくれる気持ち」そのものが嬉しいものです。
↓体験方ギフトはこちらがおすすめです。予算に応じて選ぶことができます。
結婚祝いの金額はどう決める?
結婚祝いの金額は、相手との関係性や地域の習慣によって異なりますが、一般的な相場を参考にしながら決めるのが良いでしょう。
一般的に、友人や同僚には1万円~3万円、親しい親戚には3万円~5万円、兄弟姉妹には5万円~10万円が目安とされています。ただし、地域によって習慣が異なるため、事前に確認することが大切です。
また、相手との関係性も考慮する必要があります。たとえば、普段から特に親しい友人なら少し多めに包むこともできますし、そこまで深い付き合いがない場合は相場に沿った金額にするのが無難です。
なお、ご祝儀を偶数の金額にするのは「割り切れる=別れを連想させる」として避けるのが一般的です。ただし、最近では「2万円はペアを意味してむしろ縁起が良い」とされることもあり、地域や相手の考え方によって柔軟に判断するとよいでしょう。
結婚祝いは金額だけでなく「気持ち」が大切です。無理のない範囲で、相手に喜んでもらえるような贈り方を心がけることが重要です。
結婚祝いをもらってないからあげないでいい?相手別の対応方法まとめ
- 結婚祝いは必ずしも贈るべきものではなく、家庭や個人の価値観による
- 兄弟間でお祝いの習慣があるかどうかを確認するのが重要
- 親戚からの結婚祝いは家系や地域の文化によって異なる
- 友人がお祝いをくれない場合、忘れている可能性もある
- 結婚式を欠席した相手がご祝儀を渡さないケースも珍しくない
- 自分がもらわなかったからといって、相手に贈るかは自由
- 過去の対応を考慮しつつ、自分が納得できる行動を取ることが大切
- 結婚式をしないとお祝いをもらえないこともある
- お祝いがないからといって、人間関係を悪化させる必要はない
- どうしても気になる場合、相手の結婚時にどう対応するかを判断材料にする
- 結婚祝いの金額は関係性や地域の習慣に合わせる
- もらって嬉しい結婚祝いは、実用性の高いものや体験ギフトが人気
- 結婚祝いは形式よりも「気持ち」が重要
- 祝福の言葉だけでも十分に喜ばれることもある
- 「もらえないのは悲しい」と感じたら、自分からお祝いする側になるのも一つの方法